本日は推拿クラス@上海中医薬大学附属日本校。
テーマは推拿学概論。
いつものように、チェックインをしてから授業に入りました。
推拿の定義と歴史認識についてお話しました。
まず、推拿とはなんぞや?です。
この問いに答えるのも実はなかなか困難なこと。
あれこれ悩んで、教科書に載っている言葉を使うことにしました。
「薬物を使わず、手技により疾病を予防・治療する方法であり、人類が長い歴史の間に、日常生活や闘病生活から自然に考え出し、発展させてきたものである。」
さすがは、教科書ですね。
自分の言葉で表現しようにも、教科書のまとまり具合は何ともうまくおさまっているように感じられます。
次に、「中国医学の歴史」を参考に外治法の起源と推拿の歴史認識についてお話しました。
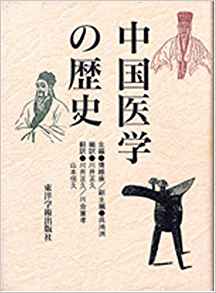
今回ピックアップした古代文献は以下5つ。
・黄帝岐伯按摩十巻
・五十二病方
・肘後備急方
・小児按摩経
・小児推拿秘旨
今回資料を作成するなかで、これらの文献をピックアップするのに一番苦労しました。出来上がってしまえば、何でもないことなんやけど・・・、あれも大事、これも大事となると収拾がつかなくなって、気がつくと頭がグルグル回ってしもてました。
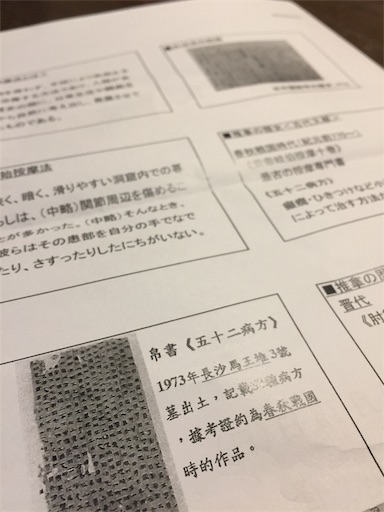
少し休憩をはさんで、米枕を使って基本手技の練習タイム。
今回は揉法(親指、母指球)の練習にじっくりと取り組みました。
手指の扱いに慣れると、次は座位にて肩部への施術を練習します。
昼食休憩のあとは、座学で<推拿療法の作用原理>について。
・調和陰陽 臓腑機能の調整
・扶正袪邪 体質増強
・疏通経絡 不通則痛、通則不痛
・行気活血 気血不和、百病乃変化而生
・舒筋緩急 筋肉を緩める
・通利関節 関節調整
この作用原理だけでも、気になるところを掘り下げれば中医理論の理解に繋がりますね。クラス内では、陰陽バランスという一見都合のよさそうな言葉を掘り下げて、中医学の中心である≪五臓のはたらきを知る≫重要性についてお話しました。
その後はベッドを使って基本手技の練習。
揉法を使って、前太腿やふくらはぎ、臀部への施術を練習しました。
最後は少林内功の練習です。
歴史上、推拿と気功は一心同体といえる関係性があります。
”推拿の上達には気功の練習が一番だよ!”
上海でお世話になった先生に教わったことをよく思い出します。当時はこの言葉の真の意味が理解できていませんでしたが、今なら少しは理解できているかな?
推拿上達へ向けて、まだまだ勉強です!!!